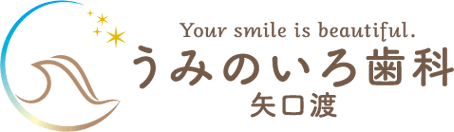2025年11月10日

こんにちは。
大田区のうみのいろ歯科矢口渡です。
「最近、食事のたびに歯に物が挟まる…」と感じることはありませんか?40〜50代になると多くの方が同じような悩みを抱えますが、年齢のせいと思って放置してしまうのは危険です。実は、歯に食べ物が挟まりやすくなる背景には、歯や歯ぐきの健康状態の変化が隠れていることが多いのです。今回は、食事が歯に挟まる原因と歯科でできる改善方法について解説します。
■歯ぐきが下がることで隙間ができる「歯周病」

歯に食べ物が挟まりやすくなる最も多い原因のひとつが、歯周病による歯ぐきの退縮です。
健康な歯ぐきは歯の根元をしっかり覆っており、隣の歯と歯ぐきとの境目もピタッと密着しています。しかし、歯周病が進行すると歯ぐきの炎症によって歯を支える骨が溶け、歯ぐきが下がってしまいます。すると歯と歯の間に「三角形のすき間(ブラックトライアングル)」ができ、食べ物が挟まりやすくなるのです。
初期のうちは軽い出血や歯ぐきの腫れだけでも、気づかないうちに歯周病は進行します。「歯が長くなったように見える」「歯と歯の間に空間ができた」と感じたら、歯周病が原因かもしれません。歯科医院では、歯石除去や歯周ポケットの清掃などを行い、炎症を抑えることで進行を止めます。重度の場合は、歯周外科治療によって下がった歯ぐきを再生させることも可能です。
■歯並びや噛み合わせの変化も原因に

もうひとつ見逃せないのが、歯列不正や噛み合わせの変化によるものです。歯は日常生活の中で少しずつ動いていくもので、特に食いしばりや歯ぎしりのクセがある方では、歯に強い力が加わり続けることで歯並びが変わってしまうことがあります。歯がほんのわずかに傾いたり、位置がずれたりするだけで、歯と歯の接触点が弱くなり、食べ物が挟まりやすくなることがあります。
このような後天的な歯列不正は、見た目だけでなく、噛み合わせや清掃性にも影響を及ぼし、歯周病やむし歯のリスクを高める要因にもなります。歯科医院では、噛み合わせの調整やマウスピースによる食いしばり対策のほか、必要に応じて部分的な矯正治療を行うことで改善が期待できます。
■「歯に挟まる」状態を放置するとどうなる?

食べ物が歯に挟まった状態をそのままにしておくと、隙間にプラーク(歯垢)が溜まりやすくなり、むし歯や歯周病がさらに悪化してしまいます。また、頻繁に同じ場所に食べ物が挟まると、歯ぐきに慢性的な炎症が起こり、出血や痛みが出ることもあります。
つまり、「挟まる」というのは単なる不快感だけでなく、歯の健康が崩れ始めているサインなのです。
■歯科での診断と改善のステップ

歯科医院では、まず歯周組織検査やレントゲン撮影によって、歯ぐきの状態や骨の減り具合を確認します。そのうえで、原因が歯周病にあるのか、噛み合わせの問題かを見極め、最適な治療方針を立てます。
歯周病が原因 → スケーリング・ルートプレーニング・歯周再生治療など
噛み合わせの変化が原因 → 噛み合わせ調整・マウスピース・矯正治療など
補綴物(詰め物・被せ物)の不適合が原因 → 詰め直しや再製作
このように、原因を明確にすることで根本的な改善が可能になります。
■自宅でできるケアと、早めの受診の大切さ

もちろん、毎日のケアも欠かせません。歯間ブラシやデンタルフロスを活用し、歯と歯の間を清潔に保つことが大切です。ただし、力を入れすぎたりサイズの合わない歯間ブラシを使うと、かえって歯ぐきを傷つけてしまうこともあるため、歯科で正しい使い方を教わると安心です。そして何より、「最近食べ物がよく挟まるな」と感じた段階で、早めに歯医者に相談することが重要です。放置せず、原因を正しく見極めることで、歯ぐきの健康を守り、将来の歯のトラブルを防ぐことができます。
■まとめ

食事のたびに歯に挟まるのは、決して年齢のせいだけではありません。歯ぐきの退縮や噛み合わせの変化など、治療によって改善できる原因が潜んでいることが多いのです。
「ちょっとしたこと」と見過ごさず、ぜひ一度歯科医院でチェックを受けてみましょう。